結婚式というと、教会での誓いの言葉や指輪の交換を思い浮かべる人が多いでしょう。
けれど日本各地には、古くから受け継がれてきた“地域ならではの結婚儀式”があります。
今回は、北陸・福井県で今も語り継がれる2つの伝統行事――
「一生水」と「饅頭撒き(まんじゅうまき)」をご紹介します。
一生水(いっしょうみず)|“この家の水を一生飲む”という誓い
「一生水」は、結婚式当日、お嫁さんが嫁ぎ先の家に入るときに行われる儀式です。
お嫁さんは玄関で一升枡に入った杯を受け取り、その中の水を飲み干します。
そしてその杯を床に叩きつけて、パリンと割るのです。
この一連の動作には、こんな意味が込められています。
- 「一升」と「一生」をかけて、“この家の水を一生飲みます”という誓い。
- 杯を割ることで、“二度と後戻りはしない”という覚悟を示す。
かつては家の井戸から汲んだ水を使い、
家と家との結びつきを強く意識する神聖な儀式とされていました。
饅頭撒き(まんじゅうまき)|幸せをみんなに分けるお祝い
もうひとつ、福井の結婚式でよく見られるのが「饅頭撒き」。
新郎新婦や家族が高い場所からおまんじゅうやお菓子を撒き、
集まった人々がそれを拾うという、なんとも賑やかな風習です。
「幸せのお裾分け」という意味があり、
地域の人たちと喜びを分かち合う目的で行われてきました。
最近では自宅よりも結婚式場で行われることが多く、
中には饅頭撒き専用スペースを設けている会場もあるほど。
参列者が袋を広げて饅頭を拾う光景は、まるでお祭りのようです。
まとめ|結婚は「誓い」と「分かち合い」
福井県の結婚風習には、
- 「一生水」:家に入る覚悟を示す儀式
- 「饅頭撒き」:幸せを分かち合う儀式
という、対照的でありながら共通して「人のつながり」を重んじる文化が息づいています。
形式が変わっても、“絆を結び、幸せを願う”という心は今も変わりません。
旅先で耳にしたら、ぜひその背景にある思いを感じ取ってみてください。
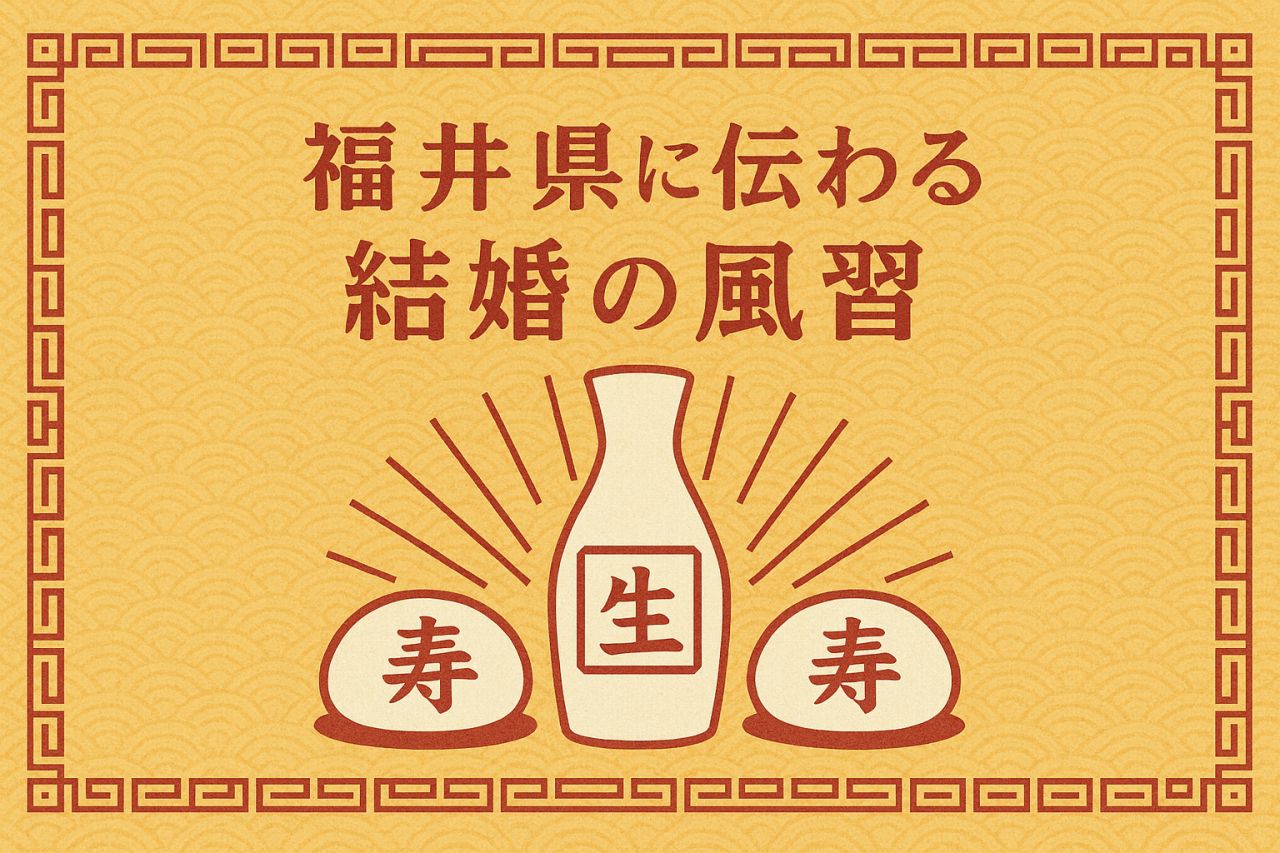

コメント